 画像・写真
画像・写真 画像・写真
画像・写真
![]()
  『それがいつのことだったのか思い出せない。 2』 撮影機材:OLYMPUS μ-Ⅱ フィルム:AGFA vista 400 2003年9月頃 ? いままでよく使っていた写真屋さんは、勤めていた職場の最寄り駅のそばにあった。 店のなかに入ると、なぜか鳥(オウム?)が飛び回っている店だった。 はじめて入ったときに名前を聞かれて「△×です」と答えると、愛想のいいこの店の奥さんが「ああ、○×さんですね。息子さんですか?」と言いながら、サラサラとお客様の欄(らん)に読みは同じで字が違う、別の人の名前を書き込んでいった。 それ以降、「○×さん」の息子と勘違いされたまま、私は長いあいだこの店を利用していた。 この写真屋さんからすると、私はそうとう「困ったちゃん」なお客だったと思う。 この店に限らず、ミニラボ(カラーネガフィルムを現像・プリントする機械)を設置している、まちの写真屋さんのおもな収入源はいわゆる「同時プリント」である。 それなのに私ときたら、この店で「同時プリント」の注文をほとんどしなかった。 私がこの店に頼んでいたものは、たいていはモノクロフィルムの現像とベタ焼き(コンタクトプリント)か、カラーのリバーサルフィルムをスリーブで現像してもらうかのどちらかだったのだ。 この店のダンナさんは、口ヒゲ・メガネ・グレーのチョッキという姿で、立ち読み客をハタキで追い払う古本屋の店主のような雰囲気のおじさんだった。 私がモノクロやリバーサルを持って店にやってくると、ダンナは露骨に嫌な顔をした。 さすがに口には出さないけれど、 「モノクロ現像やベタ焼きくらい、自分(の家)でやってくれよ!」 「リバーサルなら、もう少し歩けばプロラボ(フィルム現像やプリントを専門におこなうプロ向け(?)の現像所)があるだろうに!」 と、ダンナの顔には書いてあった。 そして、サービス(嫌味?)として、期限切れ直前のカラーのネガフィルムを何本か私に手渡すのだ。 このカラーのネガフィルムが、当時の私にとってものすごいプレッシャーになった。 「同時プリント」は、友達や家族、恋人と、どこかへ旅行や遊びに行ったときのいわゆる「記念写真」を撮ってくる人たちにとっては、とても親切なサービスだ。 誰かに焼き増しするとき、プリントがあると写真を選ぶのにとても便利だし、たいせつな思い出としてそのままアルバムとして保存してもいい。 (いま(現在)の写真屋さんのプリントサービスって、どうなっているのだろう?) しかし、いったいなにが楽しくて写真をやっているのか自分でもよくわからない、ひとりでフラフラとほっつき歩きながら写真を撮っている私のようなサビシイ人間の場合、「同時プリント」というのは、ただ袋がかさばる(枚数分のプリントが入っているため)だけの邪魔(じゃま)くさい存在でしかなかった。 ぜんぜん自分の「記念」にもなっていない写真であるから、アルバムに保存したりとか、何度も見返して思い出に浸(ひた)るなんてことはまずありえない。 あと、やはりこのころ(90年代終わりから2000年代始め)になってくると、フィルムスキャナを使ってパソコンに取り込むこととか、フィルムでなくデジタルカメラに完全に移行しようかとか、いろいろなことが頭をもたげてきていたこともあり、私にとってカラーのネガフィルムは、なんとなく中途半端な存在だった。 (カラーの場合、ネガよりもリバーサルのほうがスキャン(または画像処理)がしやすいと、当時は考えていた) 私としても、この写真屋さんの利益に少しでも貢献しようと、もらったフィルムでバンバン撮影して「同時プリント」を注文しようと考えないこともなかった。 ただ、ありがたく頂戴(ちょうだい)したフィルムなのだから、ダンナや奥さんに粗相(そそう)のない写真を撮らなければと思い、なにか「特別な」ことがあったときにこのフィルムで撮影してやろうと考えていた。 (この店は写真を引き渡すときに、プリントした写真を並べ、本人(お客)に自分の写真であるか、不手際がないかを確認をさせる) だが、待てど暮らせど、凡庸(ぼんよう)な私のような人間には、なにも「特別な」ことが起こらない。 (なにせ「記念写真」が撮れない男なのだから) いつのまにか、もらったフィルムだけがジワジワと増えていくことになってしまった。 「もらったフィルムで写真を撮らなければ」 と、思えば思うほど気が重くなり、ますますフィルムの数が増えていく。 フィルムの箱が2個が4個に、4個から8個に、8個から……。 「ギャアァーッ!!」 と、ホラー映画のように叫び声を出さないまでも、撮影をしないまま、みるみるうちに増殖(ぞうしょく)していくカラーネガフィルムの箱の山を見ることに耐えられなくなった私は、フィルムからデジタルカメラへの転向(逃避?)を余儀(よぎ)なくされたのだった。 (フィクションである。たぶん) |
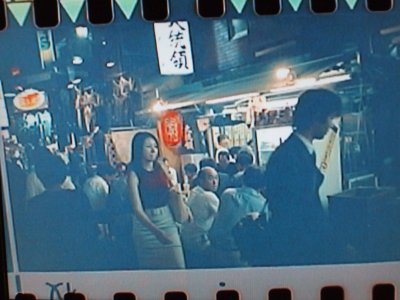 撮影は、上野のアメ横(アメヤ横丁)。  OLYMPUS μ-Ⅱ 最初に使っていた黒いμ-Ⅱが壊れてしまい、 あまったケースをFUJIFILM FinePix F10用に 使っている。  FUJIFILM デジタルフォトビジョンFV-8D 本体に、可動式のライトが付いているので、 プリント写真や立体物をテレビにつないで 見ることができる。 (追記) この写真屋さんは、コダック系列の写真店だった。 (同時プリントの裏にはかならず「Kodak」と記されている) したがって、写真屋さんでいただいたフィルムはコダック製のフィルムか、「業務用カラーフィルム」と表記されたフジかコニカ(コニカミノルタ。製造中止)のISO100のフィルムだった。 もし自分で買うとしたら、コンビニで容易に買えるものを選ぶと思うので、たぶんフジのフィルム(ISO400)にしていると思う。 それなのに、ここで使われているフィルムはなぜかアグファである。 誰かにもらったのか、どこかのカメラ雑誌に載っていた記事に影響されて自分で買ったのか、まったく覚えていない。 ネガを見てみると、フィルムの枚数表示の天地が、上・下、逆になっている。 ふつうのフィルムカメラは、フィルムの蓋(ふた)を開けて左側にフィルムを入れるスペースがあるのだけれど、OLYMPUSのμ-Ⅱは右側にセットするので、天地が逆になってしまう。 より薄く、よりコンパクトなカメラにするために、カメラのグリップ側にフィルムを入れるスペースを設けることが当時のフィルムコンパクトカメラのトレンド(流行。死語?)だった。 フィルムコンパクトカメラのもうひとつの流れは、積極的にストロボを発光させ、露出を調節することだった(と思う)。 赤目軽減の発光モードがついたり、晴天の逆光時にも積極的にストロボを発光させ、露出アンダーになるのを防ぐ機能がついていた。 μ-Ⅱも、ストロボを積極的に使うカメラだった。 にもかかわらず、私は、いちいち発光停止モードにして撮影していた。 (天邪鬼(あまのじゃく)な性格だからか?) |
| 1へ戻る | それがいつのことだったのか思い出せない。 2 | 3へ進む |
![]()
画像・写真TOPへ