 コラム
コラム コラム
コラム
![]()
SNSが苦手な私としては、年賀状は数少ない知り合いに唯一(ゆいいつ)、自分自身が『生存(せいぞん)』していることを報告できる貴重(きちょう)な伝達手段(でんたつしゅだん)である。 しかし、返信されてくる知り合いが、どのように『生存』しているのかについて、あまりにも無頓着(むとんちゃく)だったことに気づかされる。 今年(2022年)、同い年の友人から届いた年賀状を見て、私たちも、もういいかげん、自分の人生の終着点が見えてくる年齢なのだと痛感(つうかん)させられた。 1通は、富山に移住して、もう30年以上会っていない幼なじみから送られてきたもので、例年はたがいに「あけおめ」「ことよろ」的な定例文のやりとりだったものが、 旧年は何かとお世話になり 誠にありがとうございます。 とあらたまった文章のあと、がんで2回目の手術をしたことが書かれていた。 もう1通は、上石神井にあったカフェを閉店し、2018年に群馬に移住して、『芸術・茶屋』と称してあらたな店を開いた友人からで、流し絵のイラストの下に 芸術とともに生きること 日々の暮らしを大切にして そこで考える 「わからない」をゆっくり静かに考える 生きた問いとともに生きる わたしが自分で考える と書き記されていた。 私自身は、小学3年生のときにバスに轢(ひ)かれ、それ以降、精神的に不安定(社交不安障害・うつ病)で、若いころから希死念慮(きしねんりょ)に苛(さいな)まれる日々を送っていたので、いつでも人生を終わらせられるものだとずっと思っていた。 まさか、自分自身が50過ぎまで生きながらえるとは、想像もしていなかった。 ついこのあいだ、古田雄介さんの『ネットで故人の声を聴け 死にゆく人々の本音』(光文社新書・2022年)を読んだ。 がんになった彼は2020年1月から、茶屋をやっている彼は2019年11月からTwitterを利用している。かくいう私も、2021年8月からTwitterを開始した。 手術費用を捻出(ねんしゅつ)するためか、お金に関するサイトを探していたり、芸術についての自分の考えを、つらつらと書き綴(つづ)っていたり、これまで買い散らかした本を、だらだらと写真入りで紹介したりと、三者三様(さんしゃさんよう)、誰からも注目されることもなく、やっていることはたいしたことがない。 Twitterを始めたきっかけは、もちろん、死生観(しせいかん)を書き連(つら)ねるために始めたわけではない。しかし、ほんのわずかであっても、自分自身が生きた証(あかし)を残したいという思いは、やはり否定(ひてい)できないのである。 |
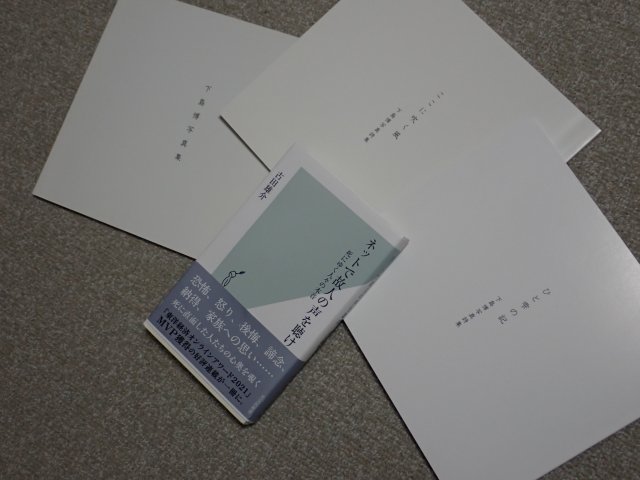 元JRP荒川流域支部の 下島博さんから 写真詩集が 送られてきました。 生きた証(あかし)をネット上でなく、 紙媒体で 残すのが理想なのかと 考えて しまいました。 |
![]()
コラムTOPへ