 コラム
コラム コラム
コラム
![]()
8月3日に亡くなったカルティエ・ブレッソンは、当時としては小型のカメラであったライカを手に、眼前で起きる一瞬の世界を、厳格なまでに(古典的な)絵画の構図を常に意識しながら捉えようとした写真家だった。 写真は絵画と同じく、四角い画面上で構成されるものだということを知り抜いていた写真家であり、また、自らが望む完璧な構図を超えたものが、写真や絵画の「表現」であることを知り尽くしていた写真家でもあった。 新たな写真表現を追及しながらも、最後まで絵画の構図の呪縛から逃れられなかった(それゆえに『決定的瞬間』(1952年)が生まれた)のは、ブレッソンが写真家としてではなく、画家としての名声が欲しかったからではないだろうか。ブレッソンは画家になりたかった(なれなかった)写真家だったといえる。 (土門拳もまた、画家になりたかった写真家といえる) それとは対照的に、絵画的思考に捉われない写真家として、桑原甲子雄の名が挙げられる。 「表現」としての写真には興味も関心も示さず、戦前から写真を撮り始め、戦後はカメラ雑誌の編集長を何誌か渡り歩いて、それでもなおアマチュア写真家としての姿勢を崩さない(「写真の「表現」を追及するのは、プロ(写真家や評論家)の仕事だろ?」と飄々としている)写真家である。 街(東京)を歩きながら、ふと目にしたものに反応して桑原はシャッターを切る。ただそれだけの写真なのだが、見る側は、どこかで同じ光景を目にしたような錯覚に陥る。 人間は、ふだんなにげなく目にしている(目にしていた)ごくありふれた光景に、注意を払わないし思い返そうとはしないものだが、その視覚情報はつねに脳に伝達され、潜在意識として蓄積されている。 その見る側の潜在意識を桑原の写真はくすぐる。桑原甲子雄の写真が現在、過去の作品を問わず、見る側にどこか不思議な懐かしさをもたらすのは、ふだんなにげなく目にしているごくありふれた光景を、桑原が無自覚に、何の意識も持たずに撮影しているからであろう。 桑原の写真は、人間の意識、無意識に関わらず、自身が目に留まる(留めた)ものすべてが、写真に成り得ることを示唆している。 では、1960年代後半、大辻清司指導のもと、桑沢デザイン研究所で写真を学んでいた関口正夫と牛腸茂雄の場合はどうだったのだろうか。 彼らは、ごくありふれた日常の光景の中に潜む「何か」を、写真に定着させようと試みた。こうした彼らの写真は「コンポラ写真」と呼ばれた。 1971年、関口正夫と牛腸茂雄は共著で『日々』という写真集を自費出版する。 デザインの学校に通っていたのだから、(絵画的な)構図を意識した写真も撮影できたはずだが、彼らはそれをしなかった。その当時の彼らには、ブレッソンや土門拳のような(報道)写真はステレオタイプな「表現」として映っていたのだろう。 桑原甲子雄のような写真を彼らは追い求めていた訳ではない。彼らは桑原と違い、「表現」者としての「自意識」が過剰なほどあった(「プロ」の写真家になりたかった)ため、なにげなく目にしているありふれた光景を自覚的に捉えようとしていた。 (その当時、桑原は写真雑誌の編集長として、彼らの写真を見る側の人間だった。もしかしたら、桑沢デザイン研究所で学生だった頃の彼らは、まだ桑原の写真をまだ見ていなかった可能性がある) 『日々』を出版した時点の関口と牛腸は、ごくありふれた日常の光景の中にに潜む「何か」について、まだどのようなものかを把握できないまま、「何か」が映っている(映っていそうな)写真をランダムにセレクトしていったものと思われる。 したがって『日々』という写真集は、彼らの意図する「何か」が見つけにくく、「何か」が見つからなければ、見る側が平凡でつまらない写真と受け取ってしまう問題を抱えてしまっている。 (『日々』に掲載されている牛腸の写真は、『デジャ=ヴュ』の牛腸茂雄の特集号で確認できたのだが、関口の写真をまだ見ていないので、これはあくまで推測である) 関口正夫と牛腸茂雄は『日々』以降、それぞれ別のスタンスから「コンポラ写真」を撮影していくこととなる。 牛腸茂雄は『日々』以後、1983年に36歳で急逝するまでのあいだに、『SELF AND OTHERS』(白亜館・1977年/1994年・未来社)、『見慣れた街の中で』(1981年・私家版)という2冊の写真集を出版した。 『SELF AND OTHERS』では、「コンポラ写真」では軽視していた構図にメスを入れることで、『日々』が抱えていた問題を克服している。 この写真集は「自己と他者」というテーマで撮影した人物のポートレートであるが、牛腸は広角レンズのパース(透視画法)を利用して、人物を「点」、背景を「線」と捉えて撮影している。 牛腸の写真(四角い画面)に対角線を引くと判りやすい。画面の中心となる対角線の接点に、牛腸は人物を配している。広角レンズを用いることで遠近感が強調され、見る側はありふれた平凡な写真であると認識しながらも、目は無意識のうちに人物の方へ吸い込まれていくことに気づくはずだ。 また、牛腸はカメラを平行に構えず、わずかに斜めに傾けて撮影している。納まりのよい安定した構図をわずかに傾けることで、見る側に違和感(不安感)を与え、主題となる人物をより注視するような仕掛けがほどこされている。 『見慣れた街の中で』では、さらにパース(透視画法)が誇張されていく。牛腸自身は、こうした構図を駆使した写真ではなく、「コンポラ写真」の特徴である、日常の光景の中に潜む「何か」という、ある種精神的な部分を探求していきたかったのだろうが、彼にはそれを追求する時間(体力)がなかった。 関口正夫は『日々』以降、写真の世界で表沙汰に取り上げられることはなかった。 しかし、関口は昨年の冬、『こと 1969−2003』(関口正夫事務所・本体価格5000円)という写真集を出版する。 この写真集を見ると、関口は頑(かたく)ななまで、『日々』のときと同じスタンスで撮影し続けていたことが判る。 (まるで『日々』の経年変化を測定し続けてきたかのようだ) 長い年月を撮影し続けるうちに関口は、ごくありふれた日常の光景の中に潜む「何か」が、いったい何なのかということには、まるで興味を失ってしまったかのように思える。関口にとっては、今現在でも、「何か」が存在していることの方が、むしろ重要なのだろう。 「何か」があるから、関口は撮影を続ける。そうしている間にも、時はよどみなく流れ続けている。『日々』から30年以上過ぎても、ごくありふれた日常の光景の中に潜む「何か」は、変わらずに私たちのまわりに存在する。 |
|
 |
逃げ去るイメージ アンリカルティエ=ブレッソン 楠本亜紀 著 スカイドア 刊 定価 2100円 (本体価格 2000円+税) ISBN4-915879-49-6 |
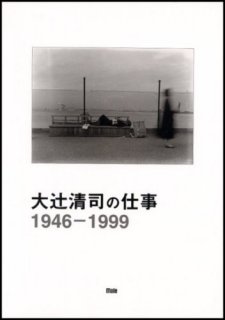 |
大辻清司の仕事 1946−1999 大日方欣一 編・著 モール 刊 定価 3990円 (本体価格 3800円+税) ISBN4-938628-44-X (在庫 僅少) |
 |
こと 1969−2003 関口正夫 著 関口正夫写真事務所 刊 定価 5250円 (本体価格 5000円+税) ISBN4-9902007-0-5 (在庫 僅少) |
![]()
コラムTOPへ