 荒川流域支部の面々
荒川流域支部の面々 荒川流域支部の面々
荒川流域支部の面々
![]()
 下島さんの支部展 出品作『高尾山』 |
西井一夫の『日付のある写真論』(青弓社・1981年発行)に、英伸三に対する写真評が掲載されている。30年以上前の文章だが、世間一般のリアリズム写真に対しての受け取られ方は、このようなものだろう。 報道写真家は、ほとんどみな、このような持続した写真取材をめざす。五年、十年をかけた写真による何かの追跡。しかし、それが本当の姿勢だろうか。もちろん、政治家の尻馬にのって去年は安保、今年は公害などと流行にあわせて写真する偽善者よりは、はるかマシには違いない。 しかし事実という奴がいつもいつも外にあり、それを追うことしかできないというのは、報道写真家の宿命なのだろうか。事実という奴を外におくことで客観を得る。だがいつだって外にあるものを事実として選びとるのは主観であるに違いない。 リアリズム写真は、社会的意義を問う写真であると私は考えているが、その作品自体は、写真家自身の倫理観によって支えられている。しかし、長期の写真取材を繰り返すことにより、社会的意義にのみ比重が増し、写真家自身が抱いていた事実への倫理観が薄れ、客観として捉えていた事実が主観へと変貌してしまう。 つまり、事実を外から追い続けるうちに、事実そのものを置き去りにし、社会的意義だけを見る側に押し付ける、独善的な写真になる危険性をリアリズム写真は、常に抱えている。 第3回目の荒川流域支部の写真展『葦笛』で、私はようやく、下島博さんの写真に出会えたような気がした。 『高尾山』という6枚組の作品は、なぜ人は信仰をするのかというところから撮影が行われているが、信仰する人々の表情を直截レンズで捉えようとはしない。下島さんは、神仏と人が関わりあう息吹を写真で表現したかったのではないだろうか。 下島さんの写真は、報道写真(ドキュメンタリー)と称される「リアリズム写真」というより、むしろ「ルポルタージュ写真」と称したくなるような、文学的な香りを醸し出していた。 この支部展の合評の二次会で、下島さんの口から、自ら旋盤工として働きながら、町工場のルポを書いている(2002年、51年間の旋盤工生活に終止符を打つ)作家・小関智弘の話が出てきて、ああ、そうなのかと思った。 下島さんは、小関さんのような等身大の労働者を描きたかったのだ。不況などの影響も重なり、職場で虐げられ、労働組合でビラを撒いている自分と同じ立場の一人の労働者の姿を見てみたい、肌で感じ取りたいという思いがあったのだろう。 事実の外に身を置く写真家としてではなく、事実の内側で耳を傾け、肌で感じ取り、自らの言葉で伝えていこうと、その当時の下島さんは、考えていたのではないか。 小関智弘の著書・『おんなたちの町工場』(ちくま文庫・本体価格580円)のこんな一説がある。 人の誠実さというものは見えにくい。妙に実直そうに作業服のボタンを上まできちんと合わせて、いつもせかせか動いている男が、自分の作った不良品(オシャカ)を他人のせいにするなんてことは、わたしもずいぶん見てきた。 下島さんのルポルタージュ・『ふたたび 種となりて』で、野田貞夫さんが、今まで苦渋を飲まされてきたであろう、日産という企業に対してこう述べる箇所がある。 「会社が俺を育ててくれたということかな」 修羅場を生きてきた人の、やさしい言葉が返ってきた。 下島さんは現在、仕事のかたわら精力的に、誠実な労働者を描いたルポルタージュを書きつづけている。 |
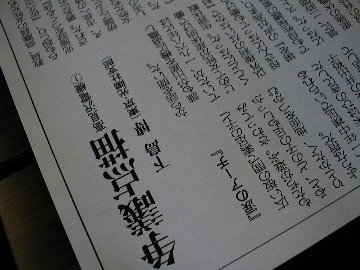 下島さんの ルポルタージュ最新作 『争議点描』 |
|
 記事の中の写真は 下島さんが撮影 |
![]()
荒川流域支部の面々TOPへ